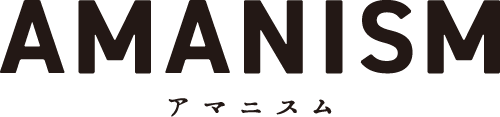「探究ランド」所長、余白探究家、フィジー留学専門家、フィジー流脱力コーチ、武蔵野大学「ウェルビーイング学部」非常勤講師、さらにコラムや著書の執筆なども……何から紹介すればいいのかを迷ってしまうほど、多彩な活動をされ、その全体像を言葉で説明しきれない人物。それが永崎裕麻さんです。
新卒で入社した会社を退職した2005年から、2年間かけて100カ国を巡る世界一周の旅へ。その後、国際的な幸福度調査でも「幸せな国」として注目されるフィジー共和国に移住し、17年ほど暮らしていました。そして2024年に、再び日本へ。暮らす場所として選んだ街は、尼崎・立花エリアでした。
なぜ立花へ? フィジーの人たちの幸せの習慣を会得してきた永崎さんの目には、このまちがどのように映っているのでしょうか。
小さな芽から始まった世界一周の旅とフィジー移住

経歴からは、旅のベテランで行動力にあふれる印象を受ける永崎さん。しかし、本人は「実はやりたいことが少ないタイプ。だから、少しでも『やってみたい』と思ったら、やらずに後悔したくない……その“小さな芽”を大切にしてきただけなんです」と意外なコメント。進学先や就職先も「これは違うかな」と、いわば消去法で選んできたそうです。
海外への“種”は、中学生時代にまかれました。「宝くじが当たったら何がしたい?」という同級生との会話で、何気なく「世界一周」と口にしたのです。当時は特別な思い入れがあったわけではなく、この種は心にそっと留まり、大人になっても心に生き続けていました。
システムエンジニアとして働き始めると、時には会社に泊まり込むほどの多忙な日々。ある日、雑誌で「世界で最も住みやすい都市ランキング」を目にし、「日本以外に、自分にフィットする国があるのかもしれない」とひらめきました。中学生時代にまかれた“種”が、世界一周の旅という芽を育てたのです。

オーストラリアから始まり、インドで終える世界一周の旅を経験後、2007年には内閣府「世界青年の船」に参加。多くの国を訪れた中で、特に印象に残ったのがフィジーの人たちでした。幸福感がにじみ出るような彼らの姿を見て、「この人たちと一緒に暮らしたら、何が起きるだろう?」とわくわくしたそうです。その気持ちから新たな芽が顔を出し、乗船中にフィジーへの移住を決めました。
出会いと体験から学び、自分の人生をデザインしていく

フィジーでは、日本人向けの英語学校を経営する日系企業で働いていた永崎さん。最も大きな影響を受けたのは、時間の感覚でした。現地の人たちはよく「一日はものすごく長い。日の出から日の入りまで、たっぷりあるだろう」と言っていたそうです。その言葉をきっかけに、「金持ちよりも“時間持ち”になろう」と考えるようになりました。
40歳を迎える頃、永崎さんは人生や時間の使い方を改めて考えるようになります。きっかけは、フィジーでの経験や40歳を定年とする考え方に触れたこと。「子どもが幼い時は親と一緒に遊んでくれますが、中高生くらいになるとそうはいきません。さらに、50代になれば体力も落ちる……だからこそ、今は家族との思い出を大量生産しようと決めたんです」

子育てを暮らしの中心に据え、子どもやその友だちと同じ目線で遊んだり、幼稚園のイベントを企画したり。当時5歳と2歳だったお子さんが小学生になった今も、そのスタイルは変わりません。そんな日々の中に、小さな芽が顔を出すきっかけがいくつもあり、それが今の活動へとつながっていきます。
尼崎は暮らしているだけで“非日常”感が十分

日本に再移住したきっかけは、医療面の安心を考えた結果でした。立花を選んだのに深い理由はなく、「親戚の家が近く、便利そうだったから」。ただ、永崎さんには尼崎に対してユニークなイメージがあり、「キャラクターの濃い人たちが多いから、自分も浮かずに暮らせるだろう」と考えていたそうです。
実際に暮らしてみると、街の人たちはフィジーの人たちにも負けず劣らずフレンドリー。「お店に入れば隣の席の人からしゃべりかけられます。『週休7日』などユーモアのある言葉が書かれたTシャツを着ていると、『にいちゃん、羨ましいわ』と、そこから会話が広がることもよくありますね。こうやって関わりが生まれる街のほうが、風通しがよくて安心できます」

永崎さんは著書で、フィジーの人たちが持つ4つの幸せの習慣として「共有」「テキトー」「現在フォーカス」「つながり」を挙げています。では、尼崎の人たちが持つ幸せの習慣をうかがってみると、「幸せより“笑い”なんでしょうね」と分析。日常の不満やトラブルさえ笑いに変えてしまう、いわば“毒々しい笑い”。その価値観こそが、この街の空気を形づくっているのではないか、「それがいいんですよ」と笑います。
「街ではいつも何かしら起こっていて、とにかくにぎやか。毎日が“非日常”」。永崎さんにとって、尼崎は好奇心をかき立てる街。その刺激の中で、物事の本質や自分の価値観について思索する……いわば哲学的な時間を過ごしているそうです。
旅するように生き、学びをシェアしながら深め続ける

「外の世界は世界一周でだいたい見てきました。これからは日本、さらに兵庫県、そして尼崎へと範囲を狭めながら旅をして、自分の内側も深めていきたい。『自分とは何か?』を理解することこそ、人生を満足して終えるためのポイントだと思うからです」
現在は、世界の文化や社会問題を学ぶオンラインプログラム「探究ランド」を、地域の学校と連携してオフラインでも広げようと準備中。さらに、日本各地のオルタナティブスクールやフリースクールを訪ね、「不登校の子どもたちに向けたお話し会をしたい」とも。
自分の中に顔を出した「やってみたい」という小さな芽に、全力で向き合う永崎さん。行く先々での出会いを楽しみ、そこで得た学びを自分のものとし、周囲にも分かち合っています。永崎さんと対話する時間は、外の世界に触れながら自分の内面をも見つめる、まるで旅のようなひとときです。


ながさき・ゆうま 大阪府出身。大学在学中に休学し、オーストラリアでファームステイを経験。卒業後は金融系システムエンジニアとして勤務。2005年に退職し、2年間で100カ国を巡る世界一周の旅へ。2007年には、国際的な幸福度調査で「幸せな国」として注目されるフィジー共和国に移住し、2024年に日本に再移住。現在は、フィジーでの学びを日本に届けるべく、著書執筆やオンライン講座(例:「余命の学校」では余命60日を仮定し、人生の終わりを体験しながら自分を再起動するプログラムを提供)の主宰、講演、コーチングなど幅広く活動中。著書に『世界でいちばん幸せな国フィジーの世界でいちばん非常識な幸福論』『南の島フィジーの脱力幸福論』『余白をつくる練習』がある。